七五三

七五三は、お子様がこれまで健やかに成長してきたことに感謝し、これからの健康と幸せを願う、ご家族にとってとても大切な行事です。
お子様が着物に袖を通す姿をご覧になって、
こんなに大きくなったんだ、と実感されることでしょう。

七五三は今も残る、
そしてこれからも大切にしたい日本の伝統文化のひとつ。
わたしたち写真館で写真を残していただくことはもちろん、
かならずお参りするようにしましょう。
七歳・五歳・三歳の祝い事である七五三は、平安時代から別々に行われていた儀式を三つまとめて行うようになったものです。
男の子も女の子も三歳になると、それまで剃っていた髪を長く伸ばして、唐子まげを結う「髪置きの儀」という儀式を行いました。男の子(江戸時代より前には男女とも)が五歳になったときには、袴をはき小袖を着て碁盤の上に立つ、「袴着の儀」を行いました。また、室町時代以降、女の子が七歳になると、着物のつけひもをとって帯をしめ、着物は振袖にかえる「帯解きの儀」という儀式を行いました。
現在では、男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳のときにお祝いをします。本来は数え年で行いますが、こどもの成長に合わせて満年齢でもいいようになっています。

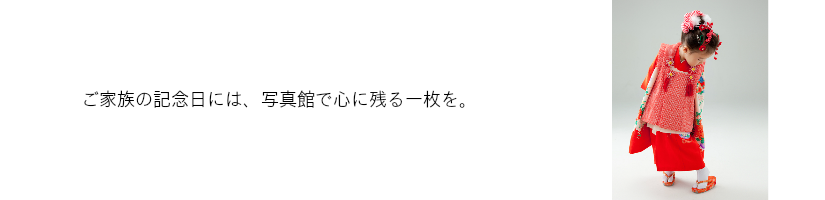
 お宮参り
お宮参り